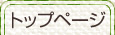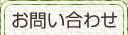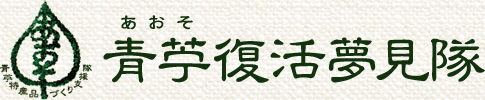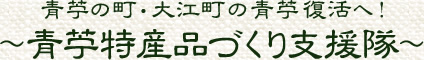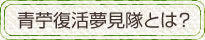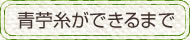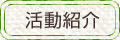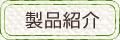草の上から
青苧復活夢見隊:2014/08/08
「猛暑」が毎日のように聞こえてくる季節になりました。
と同時にこの時期は草の伸びも猛烈です。
刈っても抜いてもまたすぐ出てくる。
野菜農家さんなどは、一通り草取りをしてスタート地点に戻ってみると、またすぐに草に追われるといいます。
とにかくうらめしい、草なんてなければいいのにと思いたくもなりますが、もし草が生えなかなったら土も豊かになりませんし、いい作物も取れません。
草が全く生えなくなってしまって、人工的にこれをやろうと思ったら、とんでもないお金と手間暇がかかります。
そう思うと、ただで勝手に生えてくる草はとても有難い存在です。
今年の青苧の刈り取りも今週で終わりましたが、青苧も考えてみると毎年毎年勝手に生えてきます。
多年草とは言え寿命がありますから、年月が経つとだんだん最初の頃のようには行かないのかも知れませんが、とにかくその旺盛な生命力には感服します。
大体、植物というものは上に上に成長します。
私は昼休みには大抵畑で横になって休んでいるので、草がとても身近です。
そのまま寝入って夢を見ている時もあります。
最近は「夢をチカラに」とか「夢をカタチに」といった言い回しもよく耳にもしますが、「将来の希望」といった意味で使われるようになったのは「Dream」を訳した明治以降だそうです。
それ以前は、どちらかというと「儚いもの」という意味で使われていたのではないでしょうか。
そもそも夢の語源は、「夕暮れに草むらで何か見ようとするが何も見えない」というものです。
転じて、目をふさいで見る夢の意になりました。
夢は目で見るものであって、かつ儚いものということがよく分かります。
対して、古来から使われてきたものに志があります。
「志」という字は、草木が伸びてゆく姿をかたどった象形文字の「之」の古形と、心臓を示す象形文字の「心」を組み合わせたものだそうです。
また、「之」は足の形が変形したもので「行く」という意味があります。
つまり、心が目標を目指して進み行くことを表しています。
心と足が組み合わされていることで、より具体的な行動につながることが連想出来ます。
私自身の印象で言うと、夢は個人的なもの、志は自分がその力を発揮することで社会の役に立つ、より公共心に富んだものという感じがします。
また、夢が対象を自分以外のものから見つけてくるのに対して、志は自分自身の中から探し当てる、あるいは湧き立ってくるものといった感じです。
どちらの字にも草が関わっているのは面白いところです。
日本人は世界に類を見ないほど和を尊ぶ、公共心が高い人種ということを考え合わせてみても、「夢」以前はそれぞれが分を守って公のためを一番に暮らしてきたのではないでしょうか。
西洋からやってきた「夢」が志を向こうに追いやった感のある現代。
これからは夢を追い求めるよりも、原点に帰って静かに志を見出す方向にシフトしていくのも一考です。
焼き畑2014
青苧復活夢見隊:2014/05/18
今年も焼き畑の季節がやってまいりました。
年々拡大の一途をたどる参加者数は、今年はなんと80名!
その半数を占めたのは東北芸術工科大学の学生さんたち。
新設されたばかりのデザイン工学部コミュニティデザイン学科と芸術学部工芸学科テキスタイルコースの皆さんです。
それに県庁、役場、大学の先生方、取材の方、お手伝いの方、我々メンバーなどを加えて、夢見隊史上最大の大所帯が形成されました。
これだけ大勢だと、あちこちで挨拶&立ち話が発生し、作業中も次々に相手を変えながら話の輪が広がっていきます。
作業という名のピクニック、あるいはわずか四畝の土地に放り込まれた日本人の坩堝といった感があります。
よく人海戦術とかローラー作戦などと言いますが、人が沢山いるというのはそれだけで威力です。
自分一人で80分かかる仕事が1分で終わる。
80回往復すべきところが1往復で済む。
正直、夢のような話です。
振り返ると自分がやった仕事の何十倍もの量が同時に進んでいるんですから。
ちょうど田植えが始まる時期でもありますが、昔の田植えのように村人が総出するような時も先人は同じような感慨を抱いたでしょうか。
昔も今も頼りになるのは人手(出)です。
初めての方が多い中で、一体どんな風に作業が進むだろうと段取りの心配などしていましたが、誰かが動けば自然と他の人もそれに加わる、作業が変わればいつの間にかみんなもそれをやっているといった具合で、場や状況を一瞬で察する我が同胞の長所が如何なく発揮されていました。
魚はよくあんなにパッパッと向きを変えられるなあと感心しますが、あれは頭が動いてから体が付いて行くのではなくて、一つ一つの細胞が同時に行動を起こすからあれだけ一瞬で動くことが出来るんだそうです。
群れ全体で見ても一匹一匹が細胞となることによって、全体として調和のとれた行動が出来るのでしょう。
失礼ながらそのような視点で見ると、今回の焼き畑でも、一人一人が自分の意思で動きつつ、全体としては魚の群れのごとく同じ方向を向いていたということになるでしょう。
前回、ミジンコやハエの話をしましたが、私たちは実は魚であったのかも知れません。
そして大海原の代わりに畑に火の海を出現させるや、みななんとなく故郷に帰ったような安心感と高揚感に包まれました。
人と一緒に自然の中で作業を行うというのは、私たちの細胞に組み込まれた安息の地なのかも知れません。
ペーストにする葉っぱや塩蔵する茎を摘み取ってから火入れ用の藁を敷き、火入れ後は鶏糞と菜種油粕を撒いて作業は終わりました。
前日の雨や強風の心配などなんのその、天候にも恵まれて賑やかな焼き畑でした。
ある意味、祭りのようでもあり、神が降りてきても何ら不思議のない、そんな空間だったような気がします。

ハエに追われ、ミジンコに負ける日
青苧復活夢見隊:2014/04/29
昨年七月に訪れた「越後青苧の会」さんから青苧の根を分けて欲しいというリクエストを頂きました。
今日は久しぶりにメンパーが会して、その根っこ取り作業を行ないました。
普段知ってる人でも久しぶりに会うとなると、なんとなく気恥ずかしい感じがするものです。
見た目にも「あれ、少しやせたかな」とか「髪型変えたな」とか多少の変化が見られ、気持ちの面でも馴染むまで少し時間がかかります。
人の体は三ヶ月で全細胞が入れ替わるというのですから、久しぶりに会ってちょっとした戸惑いを覚えるのも無理はありません。
そういえば、遺伝子の数というのは、人で2万2千個、ハエでも1万数千~2万個だそうです。
「万物の霊長」たる我々とハエとの差はわずかということでこれだけでも驚きですが、さらにびっくりなのはミジンコで3万1千、植物のイネに至っては3万2千個という事実です。
先頭をぶっちぎりで走っていると思われた人間は、遺伝子数レースにおいてはイネやミジンコに何馬身差も開けられていたのです。
ミジンコの遺伝子数が多いのは、昔から環境変化に対して、いろいろな反応をしているからということのようです。
例えば、ミジンコは自分が食べられそうになるとトゲを生やすなど体の形を変化させて、捕食から逃れようとします。
また、水中の酸素が少なくなると、ヘモグロビンの量を何十倍にも増やして赤くなったりします。
周囲の環境に合わせて速やかに自分を変化させる能力が人などに比べ突出しているわけです。
そうして、どの生物よりも速いペースで自らのクローンを作って繁殖する際に、遺伝子の数も倍増していくのだそうです。
そうすると、種の生き延びる能力の優劣というのは、身体の大小や頑強さではなくて、周りに合わせていかに柔軟に対応できるか、自分を変化させられるかということになります。
イネが人やミジンコよりも遺伝子数が多いのは、植物は基本的に場所を動かないため、より環境に対する適応能力を持っているからではないかと思います。
そうした目で見ると、スコップで力任せに掘り返している青苧の根っこもとんでもなく高等な生命体であと思えます。
「俺たちの知らない能力どれだけ隠してんの?」と思います。
果樹栽培でも、いろいろと勉強して良かれと思ってやったことがかえって仇になることもあり、彼我の疎通の難しさを痛感することはしょっちゅうです。
相手のことを知らない内は、余計なことは出来ません。
こうして、自分の脳みそと植物とで見えない会話をする楽しさはやはり現場に出ないとわかりません。
今年も青苧の作業がスタートを切りました。
変わらず日々の雑感を記していきたいと思います。

- ひなまつりと青苧研究報告会のお知らせ
- だんごさし
- 完売のおしらせ
- 小正月行事開催のお知らせ
- テレビ放映のおしらせ
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ③
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ②
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ①
- 伝統食のつどい2024
- 青苧御膳2024③
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2019年5月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年10月 (2)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (1)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (1)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (1)
- 2012年2月 (2)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)