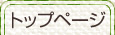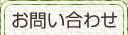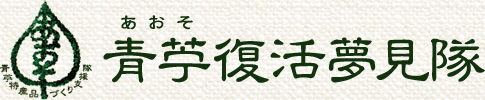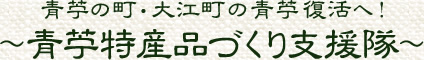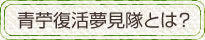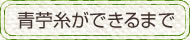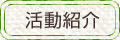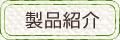自分の寝床
青苧復活夢見隊:2012/04/03
自分用青苧パッドを購入しました。
以前の試作第一号は企画展があれば展示したり、どこかに見本として持って行ったりで試しに使ってみるというわけにはいきませんでした。
まずは実際に使ってみないと分からないということで村上代表、柏倉隊長、私と新たに三枚金澤屋さんに注文したのでした。
今回のは第一号より若干幅も大きく、生地の色も表が藍色、裏が白となかなか素敵な風合いです。
いざパッドを広げてみるとまずはあの独特のシャリシャリ感がなんとも言えません。
布団を敷くのにこれほどウキウキ、ニンマリすることもあまりない。
「これからこれで寝るんだ~」という就寝スイッチの切り替えにもなります。
私は冬の間は布団の上に毛布を敷いて寝ていたので、いきなりパッドに変えたことでこれまでと違うなという気はしましたが寒くはありませんでした(青苧は湿度の調整能力が高いので、夏は涼しく冬でも冷たさを感じにくいのです)。
寝心地としてはシャリシャリが摩擦の役目を果たすのか、体が流れるということがありません。
身体と青苧がピタッと一体になっている感じ。
そして手で触っている時にはシャリシャリする音が、寝てみると全く気にならない。
これは面白いなあというのが初夜の正直な感想です。
先日、静岡の大井川葛布さんを訪問した際、親方が「『衣食住』というように、人が生活していく中で一番大事、かつ手にするのが難しいのが『衣』なんだ」というようなことを教えてくれました。
『食』は採集、狩猟、栽培にせよ、手段はいろいろあり、割合苦労せず手に入れられることも多い。
『住』については雨風さえ凌げれば、それこそ洞穴のようなものでも事足りる。
でも『衣』は動物の皮を利用するなどの方法でなく、植物の繊維から着るものを作る場合途方もない労力と時間が必要です。
よく事故などで生き埋めになったまま何日も何も口にしないで過ごしたなどの例が見られるように、食べ物がなくてもある程度の期間は生存できますが、例えば冬の寒さの中に丸裸で放り出されて何日も生きていけるものではありません。
私も去年一年青苧栽培全般に関わってみて、一枚の布、一本の糸を作ることがどれほど時間と根気の要ることか身をもって体験しました。
現在は糸や布、着るものなどは身近に溢れていて、高価な代償を払わなくても簡単に手に入れられるので、これまでそういうものに思いを馳せることが全くなかったわけですが、自分の経験と親方の言葉をつなぎ合わせてみるとむべなるかなと思います。
私は農業者でもあるので、食べ物を栽培するのと衣服を作るのとどちらが大変かと言われれば、実体験としてその答えは明白に出せます。
現代日本では『食』のことは何かと話題になりますが、『衣』についてはほとんど誰の意識にも上らなくなりました。
自分の身に付けるものを自分で栽培することがなくなった、作業が機械化されて自分の手で生み出す必要がなくなった、そのことが『衣』を日常の場面から遠ざけたのだと思います。
逆に言えば、それだけ自分達でそういうものを作るということがしんどかったのでしょう。
今回はそんな思いも手伝って余計に貴重に思えるパッドですので、しみじみと体全体で寝床を味わいたいと思っています。

春遠からじ
青苧復活夢見隊:2012/03/30
静岡に葛布&木綿見学に行ってきました。
思えば東京より西に行くのは何年ぶりだろう。
温暖な気候、柔らかな日差し、雪のない光景。
毎日を雪に囲まれて過ごしてきた身としては、雪がないことに肩の荷がすっかり軽くなったように感じられました。
こんなに違うのね~。
見事な晴天の下を心地よい風に吹かれながら歩いていると、山形の冬の曇天がなんだか遠い国のことのように思えます。
極端に言うとこの晴天の下では何でも出来るような気さえしてくる。
気候ってこんなにも人の気分を左右するもんなんですね~。
そして東北の冬はやっぱり厳しいです。
さて、この旅の一番の目的であった青苧原麻を使った新製品開発については、ありがたくも葛布の親方とおかみさんのご協力をいただきながら進めていけることになりました。
そして木綿見学に行かせていただいた先生のお宅では矢のように飛んでくる薀蓄に圧倒されつつも、豊富な知識と実技によってたくさん勉強させていただきました。
さらに旅のきっかけを作ってくれた金澤屋のブログ係長にはいろいろ楽しい思いをさせてもらいました。
係長がいなかったらこの旅は実現しなかった。
お三方に感謝。
この先の展開が楽しみです。
さて、山形に帰ってみると意外や意外、わずか3日ほどの間に景色は一変。
畑の雪も土に吸収されたか、水蒸気となって空気に舞ったか、かなり消えていました。
いよいよ山形も春近し、です。
企画展終了 蘇生再生転生
青苧復活夢見隊:2012/02/29
東北芸工大での『蘇りの青苧』企画展が今日無事に終了しました。
やはり芸工大で、ということもあってか、それぞれのお客さまの青苧への興味の持ち方、関わり方などが様々だったように思います。
人数的には歴史民俗資料館の時よりは少なかったのですが、今回は食事コーナーや体験教室などはなかったので、より青苧そのものに何かしらの思い出や目的があっていらした方が多かったのではないかと思います。
NHKや山形新聞でも取り上げていただいて、少しずついろんな方面へ広がりが出てきたなあと実感しています。
芸工大の先生や学生の皆さんには今回の企画展でも多大なご協力をいただき、感謝に堪えません。
地域のことが地域で終わらず、業種や世代を超えて現在進行形で共有できているということは考えてみればなかなか珍しいことであり有難いことです。
それぞれ別々に生きて活動している人々を結びつける場になった。
これを確認できただけでも意義深いものがありました。
古いものを新しいものとして今の世の中に提示することは単なるものとしての「蘇り」だけでなく、技術、精神、歴史、伝統といった目に見えない部分での「蘇り」を果たすことでもありました。
今はまだ「蘇った」あるいは「蘇りつつある」という段階ですが、同じものが蘇るというだけでなく、別のものとして生まれ変わるくらいになれば本物でしょう。
『生まれ変わりの青苧』展が開催できるのはいつかな・・・?
- ひなまつりと青苧研究報告会のお知らせ
- だんごさし
- 完売のおしらせ
- 小正月行事開催のお知らせ
- テレビ放映のおしらせ
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ③
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ②
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ①
- 伝統食のつどい2024
- 青苧御膳2024③
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2019年5月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年10月 (2)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (1)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (1)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (1)
- 2012年2月 (2)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)